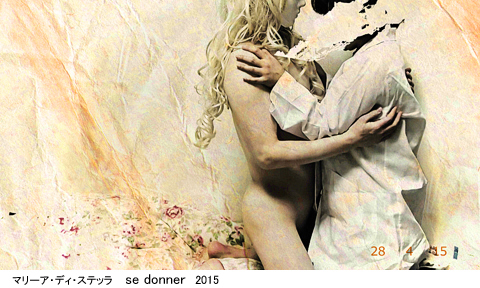
文 / 服部洋介 画像 / Maria di Stella
前回、「宗教的言説が、理性において自明でないものについて語ることであるとするならば、〈アート〉もまた宗教である」という話をした。〈アート〉のみならず、およそ〈信ずる〉ということが関わる行為は、みな宗教的である。「コンピュータ科学の分野でも、「オブジェクト指向」などという思想を言うときには、理屈では理解できない、宗教的な議論がまかり通っている」と中村八束博士は指摘する(1)。博士によると、たとえば、本来は記述法が異なる実数とベクトルの加算であっても、オブジェクト指向においては、見た目に同じ記述法が適用できるというのである。異なる演算記号を使わなくて済む上に、結果はそれぞれ自動的に示されるので大変に便利というわけだ。しかし、これの何が宗教的なのか? 「でも、誤解を与えることもあるわけだね。実数同士の足し算とベクトル同士の足し算の定義は違うわけだからね。(…)それを一つの足し算であらわすのが「良い」というところがね。「良い、悪い」ってことになると、そこは宗教だからね」(2)。
とはいうものの、結局、博士もその便利さを認めて、半ば納得の態なのだが、この種のアナロジーの濫用を問題なしとはしない。「(数学でも)ヒルベルト空間とユークリッド空間は、次元は違うけど、同じもんだって扱っちゃうんだね。ちょっと見たところ違うものを同じものとして考えられるというのはすごいことだね。ヒルベルトなら波形、つまりは波動だね、それをベクトルと考えればいいんだね。「なるほど、波動はベクトルなんだあ」と考えられるのは衝撃だったね。アナロジーでみんなが理解できるようになったというのは、一つの知的革命なのかもね。でも、アナロジーだけではどうかとも思ったけどね。2次元も3次元も無限次元も同じようにできるってのはインチキっぽいなと思ったり」(3)。
実はこの問題、トマス=アクィナスの『神学大全』でも議論の俎上にあげられている。第一問第九項「聖書は比喩を用いるべきであるか」について、その異論③は「被造物はそれが崇高なものであるほど、いっそう神に似たものになってゆく。それゆえもし被造物の或るものが神を表現するために転用されるとしたならば、かかる転用はとりわけ崇高な被造物からなされるべきであって、最下位の被造物からなされるべきではなかったであろう。しかるに後のほうの転用が、聖書のなかにしばしば見いだされるのである」(4)と疑義を呈している。神をクソみたいなアナロジーで表現するとは何事か、というわけである。主文は「聖書は万人に開かれており、可感的な対象によって喩えられるのは是」とした上で、異論に対して次のように答える。「聖書のなかで神に関することがらが高貴な物体よりはむしろ下等な物体の形象のもとにつたえられているのは適切である。それには三つの理由がある。第一に、これによって人間精神はよりよく誤解から解放されることができるからである。じっさいかかる形象が神のことがらについて固有の意味で用いられているのではないことは自明だからである。これに反し、もし高貴な物体の形象を用いて神のことがらが語られたとしたならば、この点があいまいになったかも知れない。なかんずく、物体以上に高貴なものを考えてもみることのできない人々の場合において然りである」(5)。第二には、神について「それが何か」というよりも「何でないか」ということの方がわれわれには明らかなので、似ていないものをたとえに用いることで、神がその例を超越していることについて真実に判断できるようになるとし、「第三に、かかる形象によって神のことがらは、それに値しない人々に対し、いっそう深く隠されるようになるからである」と言っている。天体などを神に喩えると、そのまま星を神だと思い誤る者が出るため、あえて卑しいものを用いて神を代替するというのである。「なんだこりゃ」と、外見だけ見てろくすっぽ考えない輩には、神の奥義は隠されてしまうのである。
アートの世界にも同じ例がある。すでにおなじみ、〈便器〉である。そこらのクソッタレな物品をもってきて「これは芸術だよ」と言い張るのはいかがなものかという議論が、それこそデュシャンの昔からあった。あわれ〈便器〉は、アンデパンダン展からお下劣の廉で放逐され、その後の騒ぎで行方不明になってしまった。これはアナロジーというよりは、アートなる語の外延に〈便器〉を付け加えようとしたものが、「〈便器〉はアートの内包に該当しない」として拒否られたというのが実際である。しかし、アートなどというのは、「それが何であるか万人において自明ではない」概念であって、〈神〉と同じく、語自体は存しても、その内包的定義は空文、外延に連なるものをいくら寄せ集めても、一なる総体について述べることのできないシロモノである。別々のものを都合のよい一語〈アート〉であらわせるのは便利だが、何かインチキくさいよなって話だ。そこへきてデュシャンは、トマスが言うような最も卑しい対象をもってきて、これぞアートとぶちあげた。トマス的定式からすると、これは崇高なるアートのアナロジーとして、極めて適切なオブジェなのである。〈便器〉なる猥褻な外見によって、アートにふさわしくない物質主義者を欺き、遠ざけることができるからである。事実、デュシャンはアートの秘教的性格について言及している。「100年前に、数人の画家、数人の画商、数人のコレクターがいて、それで芸術制作とは、一種秘教的活動になっていました。こうした人々、こうした数人の人たちは、一般の人にはわからない彼らだけの言語を話してましたし、こうした言語を彼らは、宗教的言語とか、あるいはたとえば法律用語として受けとめていました。それぞれの言葉は、秘教伝授された者にしか意味がなかったからです」「秘教主義者たちは、大衆が自らいわゆる秘教伝授された者になるに任せてしまったのです。ところが、大衆は秘教伝授された者ではまったくありません。この秘教主義は、秘教主義でも一般向きの教えになったのです。今日あなた方が絵画について話したり、今日一般に芸術について話せば、一般大衆は発言を許されますし、それを言いますよ。さらに加えて、一般大衆はお金を持ってきたし、芸術での商業主義が秘教主義の問題をその一般向きの教えにしてしまいましたよ。そうなると、芸術はインゲン豆と変わらない商品です。スパゲッティを買うように芸術を買うというわけです」(6)。
デュシャンは、芸術において「自分がほとんど反民主主義的にならざるをえないのは残念です」とさえ言っている。アートがもし理性において自明ならざる概念ならば、万人において共通の了解が成り立つことはない。それがもし理性において自明な対象、たとえば自然科学の対象であるならば、そもそも多数決はいらない。したがって、ぐにゃぐにゃの現実を多数決で押し切ろうなんてのは、考えようによっては暴挙なのである。スマリヤンの笑い話に次のようなものがある。ある日、どの映画を観るかをめぐって、スマリヤンが多数決にしようと提案したところ、10歳の少年デイビッドは、ジョン・スチュアート=ミルと同じことを言った。「多い方が勝つんだから、不公平だ!」(7)。なるほど、事実確認的ならざる命題について、どっちが正しいかなどと言い出したら宗教もいいとこである。この例え話の示唆するところは、民主主義であろうと秘教主義であろうと、芸術の善し悪しは宗教的な直観でしか判ずることができない、ということである。人文社会において多数決が理性的な意味で有効なのは、対象とする命題が自然科学のように事実確認的である場合、つまり、そもそも多数決を取る必要のない場合に限られる。デュシャンによれば、芸術における商業主義の導入は、実用物の事実確認的な評価基準を宗教的事物にも適用することで、芸術を民主化し、商品化することを可能にしたというのである。一見すると結構な話のようにも思える。
インゲン豆やスパゲッティはどこで食っても価格に大差はない。だが、実用を超えた〈便器〉の価値となると、人によっては「それ、いらねーよ」って話にもなりかねない。しかし、このプライスレスな発明に対価を支払おうというパトロンがあらわれ、気前よくデュシャンのガラクタを買ってくれたわけなのだが、これとて法外な値段ではなかった。ところが、定価がないのをいいことに、無意味なものを宣伝の力で高級化し、「マーケットで評価されて値がついてるんだから、自由で民主的でしょ」と正当化する輩が出てきたのである。いや、市場がどうのっつったって、結局は王侯貴族が趣味で金を出してるのと事情は何ら変わらんのだけどね。しかし、王侯どもはアートで儲けようとはしなかった。ボッティチェリだのダビンチだのミケランジェロだのに消尽して、メディチ家の財政は傾いちゃったわけだから。しかし、アートによる再自己固有化、つまり利殖を目論むともがらが現われた時、アートは経済的にペイする商品となることを義務づけられるようになった。それが「民主的」なる語の意味するところである。何かうまいこと語の意味がすり替えられちゃっているわけである。
目下、金融経済は実物経済の数倍の規模に膨張しており、「お金ってモノの代用品じゃなかったの」とだまされている人には大変気の毒だが、モノとは関係のないところで、マネーは日々、誰かの負債をもとに創造されている。必需財が飽和しても、労働はなくならない。なぜかというと、借金の返済が残っているからだ。利子はつけやがるし。しかし、モノよりカネが多いのにカネの価値が暴落しないのは、日々、新たな労働が作り出されているからだ。つまり、必需品以外の贅沢産業を過剰に発達させることによって、金の使い道を発明し、〈労働〉を創出してしまうわけである。今やこうした浪費的な〈消尽産業〉の方が、必需品よりも効率的にマネーを吸い寄せる構造になっており、そのことによって非実用物を売りつけることは、マネーのお墨付きにおいて経済的に正当化されるのである。しかし、経済的な有意味性とモノの実用性が同値であるとするならば、アートの場合、両者が極端に乖離していることに困惑させられる。少しくらいその効用を説明してもらいたいところであるが、それはむずかしいことらしい。「どんな秘教主義にでも、等価なものとしての言葉をもたない一種の神秘があります。あなた方にはこれらのことを言い表わすことはできません」(デュシャン)(8)。効用も機能も説明できない真の無用物、それがアートというわけだ。
他の非実用産業に比べ、内容的に理解困難であるにもかかわらず、アートの扱いがずいぶんと高級なのは確かに不可解である。そもそも理解不能なものに対し、逆説的にある種の理解、つまり〈誤解〉が働いているがために、こうした設定が可能になっていると考えるほかない。デュシャン曰く「この100年来の商業主義的介入は、芸術に何ものをも生み出さなかった」(9)。というのは、もともと実用的な機能をもたなかった〈アート〉が、〈商品〉となることで、それが嫌でも機能をもたざるを得なくなってしまったことを言い表わしている。実用物でもなければ効用もない〈アート〉を〈商品〉として扱うための広告と流通の仕組みが発展し、芸術はノーマルな商流に乗ることになったとデュシャンは考えた。そうでもしなければ、〈便器〉を見に美術館に殺到する馬鹿(私もだけど)などいない。デュシャンとしては「あんたら騙されてるよ?」とウンザリだったようだが。
とはいえ、デュシャンも飯を食わなくてはならない。おまけに彼は怠け者で働くのが嫌いときていたから、事態は深刻だ。「私には途方もない怠惰が根底にあるのです。働くことよりも生きること、呼吸することのほうが好きなのです。私がしてきた仕事が、将来、社会的な観点からみて、何か重要性を持ちうるとは考えられない。だから、こう言ってよければ、私の芸術とは生きることなのかもしれません」(10)。要するに、彼の行為は〈労働〉ではなく〈消尽〉であり、経済的要請とは無関係に好きなことをする代わりに、再自己固有化の度合も小さくてかまわないよということなのである。人間性それ自体を生の目的とし、好きなことのために人生すべてをつぎ込もうとしても、それはなかなかできないことだ。多少なりとも返報や対価を期待せずには、遠からず破滅である。芸術における非実用性、無意味性、つまり経済性の欠如は、余剰をもたない逼迫した社会において、消尽的芸術が抑圧されるであろうという推測を容易にする。つまり、人間を生産のための道具として手段化する〈労働〉へのニーズが高まるということである。経済性に基づく議論は、すべてこの範疇に属する。逆に、中世のように、救いを求める諸侯どもが、決して豊かとはいえない社会の中で、庶民から搾取した富を湯水のごとく寺院に寄進して宗教芸術につぎこむというのは、まったく消尽的である。建造した文化財でインバウンド観光を促進し、それで散財したカネを回収しようとか、そうした再自己固有化は想定されていない。もっとも、天国や来世でいい目を見ようとか、そうした利得は期待したに違いないが、それは〈労働〉の領分ではない。〈労働〉はもっと事実確認的なものだ。これこれをすれば、こんなリターンがあるということが目に見えてわかるのが〈労働〉である。とはいうものの、消尽した金もどこかで誰かの役に立っているわけで、「風が吹けば桶屋が儲かる」的なカオスな方式で、意図せずに無関係の人に恩恵をもたらしているはずだ。デリダのいう〈散種〉的な〈贈与〉である。将来のバックを期待して年金を積み立てても、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用損で日本年金機構がつぶれたとしたら、支払った金は老人世代に〈贈与〉されたことになり、自分には再帰しない。われわれなら腹を立てるところだが、この何とも気前のよい〈贈与〉は、まさに天国への近道なのである。実際、株式へのポートフォリオ偏重のせいで2015年7~9月期の年金運用損失は約7兆9000億円と試算されているわけだから、他人事じゃないね。
さて、年金は生きているうちに再自己固有化されないと困ったことになる。つまり、再帰のための円環が必要なのだ。〈労働〉における実用というのは、この「期限内におけるバックの保証」についていうのであり、〈無意味〉とか〈非実用〉というのは、贈与者に対して再帰することのない消尽を指すのである。とはいえ、自然法則とは異なり、人文社会のことであるから、〈実用〉が来世的なものに比べればいくらか目に見えて事実確認的だとはいっても、しょせんは行為遂行的な空手形にすぎない。そこでこの円環を担保するための〈契約〉が必要となる。これがエコノミーのロジックである。デリダは言う。「私は犠牲を捧げますが、それは再び利益を見出すためです」(11)。現世利益というものは、〈契約〉によって円環の〈掟〉が固定されずには保証されえない。ここに〈労働〉が〈規律〉を伴う事由が見いだされる。この束縛は〈消尽〉には見いだされない。怠け者のデュシャンにおいて、アートが〈消尽〉から〈労働〉へと変化することは、彼にとって本末転倒の事態であったことは言うまでもない。アートなんてのは、リターンを目的とするようなシロモノではないわけである。自由にやる代わりに、儲けもない。なるほど、労働のない世界は人類の憧れである。労働終焉後のパラダイスを先取りしちゃってる連中からすると、人類の理想に共鳴するパトロンから扶持を受けて、彼らの〈消尽〉によって、わけのわからん作品を好き放題に生み出すというのは、誰にも妨げられることのない人間性の発露として、実に崇高なことなのである。なので、アレンスバーグのようなパトロンからすると、芸術家に投資した資金の再自己固有化なんてのは考えの外であり、芸術家も、それを〈労働〉の円環に投げ入れようなどとは思わぬことが肝要である。つまり、芸術なんてのは、作るのも買うのも単なる〈消尽〉で、それ以外に意味はない。これがデュシャンをして「芸術は秘教主義」と言わしめた理由である。「ものを制作する芸術家は自分が何を制作するのか何もわからないし、自分が何を制作するか何ひとつ理解していないのです。(…)ですから、あなたがすべての芸術家にそれを尋ねたら、彼らはこう言うでしょう。私はばかです、私は何も分かりませんと」(12)。トマスもまた言った「われわれは神について、その「何であるか」を知ることができない」(13)と。ついつい〈労働〉の面からものを見てしまう俗人には、この秘儀は理解できないというわけだ。トマスもまた莫大な荘園を領有していたモンテ・カッシーノ大修道院の院長になるキャリアを捨て、一族の反対を押し切って乞食修道会と揶揄されたドミニコ会に入っちゃった奇人変人で、人々の喜捨に頼るという点では、ほとんどデュシャンと変わるところはなかった。
しかし、無意味な〈遊び〉の何が崇高なのであろうか? それは、人間の〈自由〉を称揚するところのゆえに崇高なのであって、反対に人間を規律で縛りつけ、忍従を押しつけ、管理する〈労働〉は、争いや不寛容の種となりかねない、なければないにこしたことのない苦役なのだ。〈労働〉なんてのは、モノが足りている時にことさらしなくてはならないものではない。一般に、〈労働〉の比率が高まるほどに、人間性は圧迫され、愛や贈与、親切心の発露は妨げられる。庶民の幸福実現のために適度な労働で十分食える社会を作るという発想に基づけば、〈労働〉というものは、頑張れば頑張るほどによいというものではないのである。アートという労働破壊的な消尽には、せいぜいそんな戒めくらいの意味しかない。要するに、「〈労働〉が自己目的化すると世界は不幸になるんだね」とか、「アートなんて生活の役には立たないけど、好きなことをするって人間らしい生き方で幸せだね」といった程度のもので、根本的には、経済問題の裏返しなのだ。ゆえにシンボリックな無意味さが求められるのである。「俺は断じて働いてないぞ!」という生き様なのである。しかし、今やそんな秘教を擁護するパトロンはいない。〈自由という名の野良犬〉(村上隆)を全部収容していたらきりがない。首輪をつけて規律を与え、契約の鎖につながなくてはならないのである。それが問題なのである。不要な労働をなくすには、マネーの大規模な消尽が必要だ。それも贈与者に再帰しない浪費であって、かつ、消尽によって過剰サービス的な労働が再喚起されるものであってもならない。この条件が満たされない限り、金持ちの濫費は労働を増大させる働きしかもたないだろう。そしてマネーの管理者は、そうした体制が維持されることを望んでおり、アートもまたそのための貢献を求められているのである。
しかし、アートという〈商品〉の性格を基礎づけるのが無用性と了解不能性であるとすれば、経済的に無意味なものを商流にのせるというのは一つの離れ業、というより、言ってることが矛盾しているわけである。現代アートのこの二重性とは、ボードリヤールの言葉を借りるなら「それ自体が(…)すでに無意味なのに、ナンセンスをめざし、うすっぺらな言葉でうすっぺらを気取る」「無価値・無内容のインサイダー取引」であり、それは「無を価値の秩序に売り渡し、悪を役に立つ目的に売り渡そうとするすべての業界人に共通する特徴」(14)なのだ。彼らは「無内容を商業的な戦略にしているだけであり、(…)無内容であることに宣伝用の形態をあたえることになった。それは、ボードレールが述べたように、商品のセンチメンタルな形態である」(15)。〈便器〉を見た瞬間、「ああ、あれね」などと現代アートのルールがわかっちゃった時点で、われわれはすでに終わっているのかもしれないね。それはすでに〈無意味〉ではない。了解可能な〈意味〉であり、それゆえに〈商品〉なのだ。ボードリヤールは続ける。「真に無価値・無内容であることは密かな特質であり、誰にでも要求できるわけではない。本当の無意味さ、意味に対する挑戦の勝利、意味の解体、意味の消滅の技法――それらはいくつかの稀な作品だけの例外的な特質であり、けっして気取りではないのだ。そこには無へのイニシエーションの形態、悪へのイニシエーションの形態が潜んでいる」(16)と。
美術の世界を支配する表象システムに壊滅的な打撃を加えた〈便器〉だが、結果的にそれは「現代アートが無価値・無内容であるはずはないので、そこには何かが隠されているにちがいないという思い込み」(17)を人々に与えてしまった。実際、〈便器〉は経済的にも思想的にも意味不明の領域に属するものであり、そこに理解可能な記号体系は存在しない。それが場違いにも美術展の会場に持ち込まれた瞬間、「世界のあらゆる凡庸さが美学へと移動し、逆にあらゆる美学が凡庸なものとな」(18)り、以後、人々は無価値なはずの〈便器〉に〔秘教的ではない一般的な〕価値があるものと誤解するようになってしまったのである。否定神学の神と同様、アートの実体もまた言語を絶する無意味なものだ。その語りえない何かを指示するために、一つの前例として〈便器〉が担ぎ出され、「こういうのがアートなんだよ」という業界ルールが習慣化し、そのスタイル自体がアートだという話になれば、そりゃ確かにインサイダー取引といわれても仕方がない。人々はついに〈便器〉自体が〈神〉だと思い誤ってしまったのである。
これらの教訓から言える結論はこうだ。〈アート〉に対する理解はすべて誤解である。かといって、心配には及ばない。ボードリヤールには怒られるかもしれないが、それが〈アート〉であるにせよ〈アート〉のふりをした〈商品〉であるにせよ、もとをただせば無意味であることに変わりはない。それゆえ〈アート〉は理解されず、〈商品〉は誤解されるのである。よって、世の芸術家たちが売れないからといって思い悩むのも一つの勘違いであり、宗教をカネの力で正当化しようなどという筋違いな評価に煩わされる必要はないのである。
(*1) 『中村八束の論理的世界』「理屈、論理そしてコンピュータ」(2009年3月9日記事),web
(*2) (*3)筆者との対話。2015年9月1日
(*4) (*5) (*13)世界の名著 続5『トマス・アクィナス』Thomas Aquinas〔著〕,山田晶〔編〕,中央公論社,1975,p.108,110,100-101
(*6) (*8) (*9) (*12)『デュシャンとの対話』Georges Charbonnier〔著〕,北山研二〔訳〕,みすず書房,1997,p.12,13,15,19
(*7) 『天才スマリヤンのパラドックス人生』Raymond Merrill Smullyan〔著〕,高橋昌一郎〔訳〕,株式会社講談社,2004,p.64
(*10)『デュシャンとの世界』Marcel Duchamp,Pierre Cabanne〔著〕,岩佐鉄男,小林康夫〔訳〕,朝日出版社,1978,p.153
(*11)叢書・ウニベルシタス281『他者の言語 デリダの日本講演』Jacques Derrida〔著〕,高橋允昭〔編訳〕,法政大学出版局,1989,p.116
(*14) (*15) (*16) (*17) (*18)『芸術の陰謀 消費社会と現代アート』Jean Baudrillard〔著〕,塚原史〔訳〕,NTT出版株式会社,2011,p.11-12,13,12,15,78
服部 洋介 Yosuke Hattori
1976年、愛知県生まれ。
長野市民。
yhattori@helen.ocn.ne.jp
http://www.facebook.com/yousuke.hattori.14
|