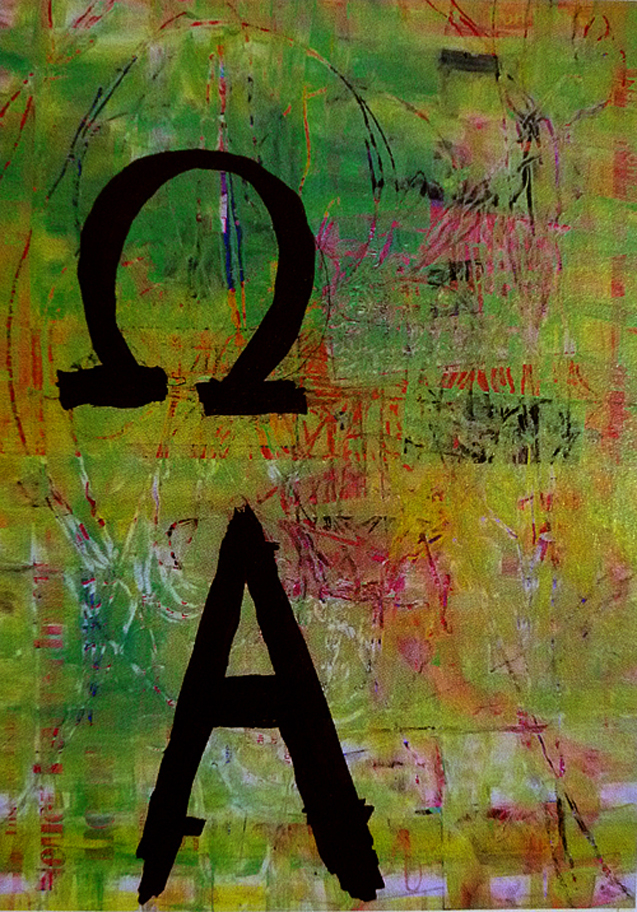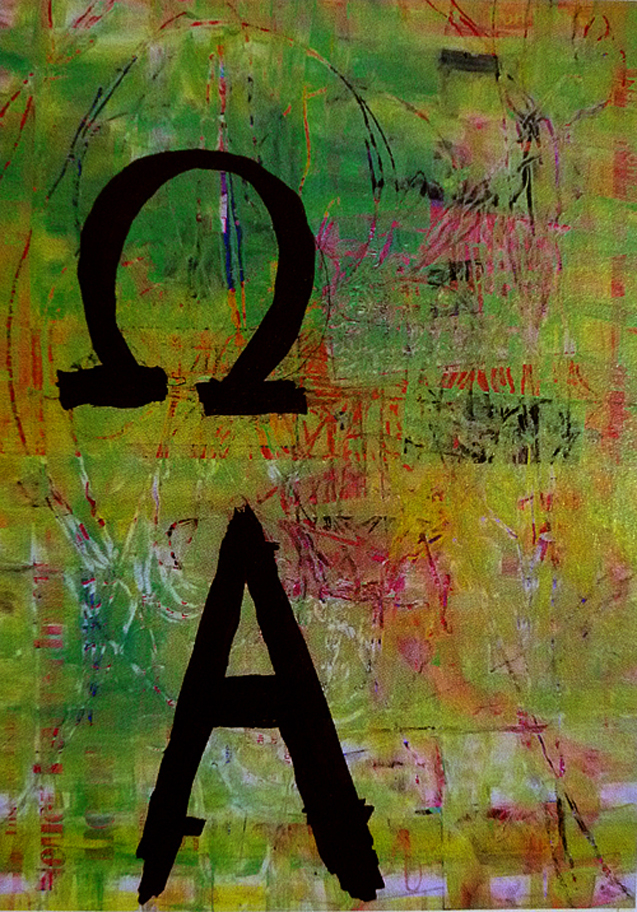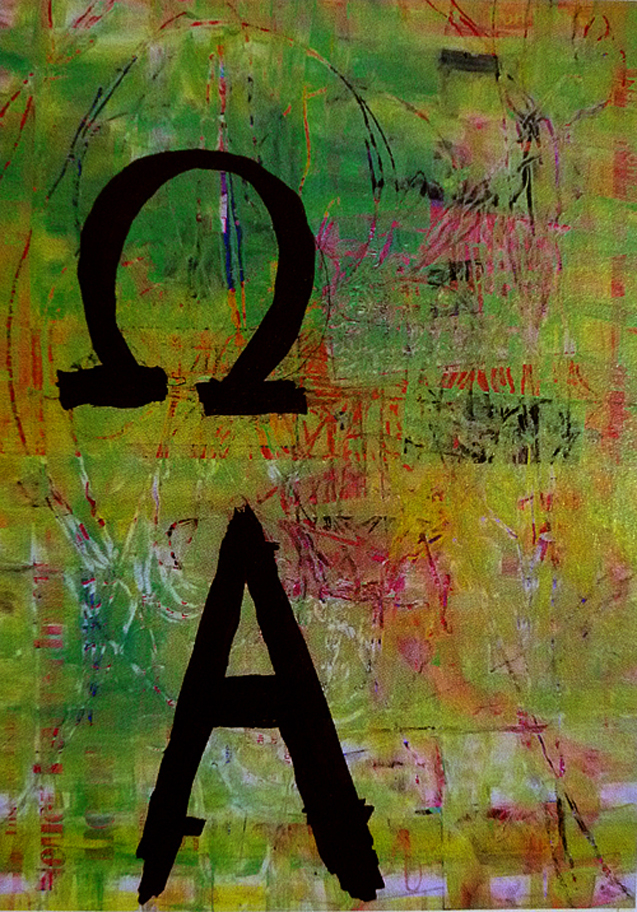 “A &Ω”Chihiro KOSHI, 2011
文 / 服部洋介
「昔は恋愛が怖かった。愛するものができると絵がやわらかくなりすぎる気がして。(…)今は全てを受け入れていこうと思うし、子どもを産んだあとの自分の絵を見てみたい」――ある対談で越ちひろ(千曲市出身)は語っている(*1)。かつて彼女は、グノーシス文献『雷、全きヌース』(「ナグ・ハマディ文書」コーデックスⅥ所収)の以下の部分をwebサイトに引用している。
我は最初にして最後の者なるゆえ。
我は誉ある者にして侮られし者。
我は娼婦にして聖なる者。
我は妻にして処女…
我は石女にして多くの息子あり…
我は把握されざる沈黙…
我は我が名の言辞。(*2)
娼婦にして聖女、妻にして処女、不毛にして多産――自己に対するこの両価的な認識は、作家のステートメントにもあらわれる。
私は、意識の及ばない時間に身体のみを委ねる。
その線や点は、私の奥から放たれる。
無意識の状態に近づけば近づくほど、表面に存在する物質は、内を叩き付ける。
魂が肉体と融合する。
その中で私が描き続けていること。
両面を持って存在すること。
女性的であり、男性的。強くて、弱い。暴力的で、狂気に満ちていて、優しく、儚く確かな存在。
華やかでダークで、生であり死であること。(*3)
「女性的であり/男性的」とは何であろう? 以下、「強くて/弱い」「暴力的で/優しく」「儚く/確か」等についても、雑駁にいえば同じ問いといえるだろう。「男である」を「女ではない」と言い換えるならば、命題「越ちひろは女である」が成り立つ時、「越ちひろは女ではない」が同時に成り立つことはない。これら、対になる組み合わせ(シジギー syzygy)の一方をA(女である)とすれば、もう一方(女ではない)は、¬A(Aではない)となろう。このような一項真理関数をベン図であらわすと、円によって限定された内部がA、その外部が¬Aとなる。Aと¬Aは共有部分(「Aであり、かつAではない」A∧¬A)をもたない。「Aであると同時にAでないものは1つもない」、つまり「無」(nullus,DBにおけるNULL)である。「無」とは「矛盾」であり、世界にあって「表現することのできない」領域をあらわしている。矛盾が真とされる時、あらゆる命題はそのままに成り立つ(爆発原理)。これは古典理論において
A,¬A⊦B
と定式化されているが、要は「AかつAではない、が成り立つとき、Bはすべて成り立つ」ということであって、一つの矛盾を真と認めるならば、そこからあらゆるものが真へと導かれることが知られている。ゆえに矛盾は恒偽命題とされなくてはならない。
だが、ある種の伝統においては、神はむしろそのような矛盾として捉えられていた。「神は全知全能」という定式も同様の矛盾を孕んでいる。神の不可知の本質を、第一ヴァチカン公会議は「闇に蔽われているよう」(quasi quadam caligine obvoluta)と表現し、ヴィトゲンシュタイン(1889-1951 以下、L.V.)は「論考」において「神は世界の中には顕われない」(「論考」6.432)といい、論理空間を規定して「矛盾命題はすべての命題の外側に消滅し、(…)、矛盾命題はあらゆる命題の外側の限界」(5.143)であるといって、矛盾から導かれる命題が論理においては常に偽であることを示した。その一方で「いい表わせぬものが存在するのは確かである。(…)それは神秘である」(6.522)といい、「時間・空間のうちに生きる生の謎の解決は、時間・空間のかなたに求められるのだ」(6.4312)とも言っている。もっとも、彼にとっての神秘は「世界の全体」すなわちA∨¬Aそのもの(トートロジーとしての排中律。「AまたはAではない」)であって、必ずしも神を矛盾と捉えていたとはいえないようである。「越ちひろは女または女ではない」は恒真命題である。L.V.は世界の半分、すなわち「越ちひろは女ではない」の部分を「マイナスの事実」と呼んだ。それは真なる命題の記述に登場しながらも、経験的には偽であり、不成立の事実である。その全体は真でありながらも、何も語らない。越ちひろは女なのか男なのか。しかし、間違いなく越ちひろはそのどちらかなのである。この問題は様相論理学に持ち越された。現実世界が成り立っている以上、可能世界が成り立たないという論理的必然性は認められない。様相実在論では「越は女ではない」というもう一方の世界の実在を想定する。だが、それはそもそも越が女であるという「プラスの事実」を欠いては予感されえない可能性であろう。
一方、「無なる神」という矛盾を人間理性は拒まざるを得ない。それは、現実の生においては成り立ちえない像である。われわれの目には、どう見てもベン図内のAと¬Aは円の内外に分割されており、円内の有界領域(A)は円外の非有界領域(¬A)とは隔てられている。平面において閉じた曲線が領域を内と外に分割するというジョルダン閉曲線定理は、われわれの生の体験とも矛盾しない。個である「私」と「私以外のもの」の混同が起こることはない。しかし、「私」の唯一性は自明のものではない。それを知るには「私以外の世界」に「私」が存在しないことを証明しなくてはならない。つまり、世界にどのような対象がどれだけ存在しているのか、原理的に全て知っていなければならないからである(全称命題は基本的に同様の問題を抱えている)。A∨¬Aは何も語らない。それは説明するまでもなく真でありながら、同時に語りえない全体である。それが分割されるにつれて、私たちはある種の不完全さについて言及せざるを得なくなる。「私」について言及することで、私たちはうっかりと世界の全体をも規定しているのである。それを回避するために、哲学は言語=世界を明晰に限定しなくてはならない。
ところで、上の閉曲線定理は、立体上では必ずしも成り立たない。先だって亡くなられた梅垣寿春博士に学び、Mizarによるジョルダン閉曲線定理の完全証明の定式化に貢献した信州大学工学部名誉教授の中村八束博士(長野市出身)は、3次元においてジョルダンの定理が破れる様子を「穴を掘って脱獄すること」に喩えている。円内に穴があったとすれば、表面をジョルダン曲線で閉じたとしても、内と外がトーラス状に連続しているため、曲線の内部(A)と外部(¬A)は分割され得ない。マイケル・スコフィールドは、フォックス・リバー刑務所のこの性質を利用して、『プリズン・ブレイク』に成功した(他の場所では無理だった、笑)
ここで画家の言葉に戻ろう。モリヤコウジとの対談で、画家は次のように述べている。
「ウロボロス」という自分の尻尾を食べて生きている神話の蛇がいます。はじまりと終わりがない、生死の両方を持つこの蛇は、永遠のマークの象徴になっているとも言われていて、それがこの世のすべてであると言われています。(*4)
彼女のwebサイト『ouroboros』(ウロボロス)には、ユング(1875-1961)の高弟エーリッヒ・ノイマン(1905-60)の言葉が引かれている。
自身を殺害し、結婚し、受胎させる者。
男にして女、孕ませる者にして孕む者。
飲み込む者にして誕生させる者。
能動であり、受動。上なるものであり、下なるもの。
これは『ユング心理学事典』(*5)の邦訳p.20「ウロボロス」の項の要約である。余談だが、東京大学総合研究博物館ニュースも『ウロボロス』という。その赤門前の大山堂書店に、かつてノイマンの『意識の起源史』(*6)が陳列されていた。その下巻p.436に「「ウロボロス状態」とは間違いなく[意識が]ゼロになる状態である」という示唆的なフレーズがある。越の言葉「私は、意識の及ばない時間に身体のみを委ねる」を思い起こしてほしい。ここに彼女の創造性の心理学的ないしパトグラフィ(病跡学)的な原点がある。
一方で、ウロボロスはグノーシス的なキリストのシンボルでもある(パリ国立図書館の錬金術史料「写本2327」等を見よ)。ノイマンの前掲書〈上〉には「ウロボロスは、《全は一なり》の元型としていたるところに見られ、(…)「私はアルパ(筆者註・アルファ)でありオメガである」と自らを明かした原存在としても現れている」(p.42-43)とある。『ヨハネの黙示録』「神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。「わたしはアルファであり、オメガである」」(1:8, 新共同訳)を踏まえているのは言うまでもない。「始まり」(A)はすなわち「終わり」(Ω)であるという言明は、素朴に言えば矛盾を含んでいる。ノイマンは、ウロボロスというシンボルの最大の特徴が「規定されず、規定しえないもの」、すなわち無限定性にあると指摘する。彼はそれをユダヤ教神秘主義におけるエイン・ソフ(絶対無)に喩えた。全てが可能な爆発的な領域(矛盾的な無)から、L.V.のいう神秘としての世界の全体へ、そして、三値論理的な未知や可能性の領域を捨象し、真偽が一方に確定した現実へと、世界は次第に分化し、意識において明晰となるのである。
ここにドーナツがある。ドーナツとは円柱を曲げて上面と底面をつなげたウロボロス的立体だが、ドーナツの表面に立って、これを輪切りにするようにして円(meridian)を描くと、円によって閉じられたはずの内が、外とつながったままであることがわかる。ウロボロス=ドーナツ立体(solid torus)の表面においては、時にAと¬Aは一体のものとしての表現をとりうる(直観主義的に拡張されたハッセ図を連想させる)。だが、平面に喩えられる私たちの生の存在形式においては、たとえ宇宙がそのようなメタな構造を有していたとしても、そのような宇宙のふくらみをとらえることも、事物を上のように分割することもできないだろう。少なくとも、こうした世界を描くには、キャンバスをもう一次元、追加しなくてはならない。「無」は存在(有)における内的な表現形式を超えている。人は世界の不在を思考することはできない。世界の中に「無」を見出すことはできない。観測のあるところ、否応なく世界は存在する。その中にあって、まさしく思考できないもの――Aであり、同時にAでないもの、AにしてΩ――それがあらゆる人間的な形象を放棄した否定神学の神であり、量子力学における観測問題であり、精神分析学派の考えるところの無意識というアナロジーであった。記述に即応する対象が論理的に存在しない――それを意味の通る文章として示すことはできても、本当の意味でそれを現前に表現することもできない。という意味では、あらゆる芸術「表現」は、A∧¬Aというよりは、A∨¬Aのうちに含まれる。Aが成り立つということは、それだけで「Aが成り立たない」可能性をも自動的に現出させる。そこまで含めて恒真命題は成立する。それは常に真なる形式である。たとえAが真であっても、偽なる¬Aを加えてかまわないということになる。「かぎられた全体としての世界にいだく感情、これこそ神秘的なものだ」(6.45)は、アートが成り立つ余地を指すかのようである。越ちひろは男または女であり、処女または母なのだ(*7)。相反するものが全体として示された時、それは常に真なのである。「世界がいかにあるかが神秘なのではない。世界があるという、その事実が神秘なのである」(6.44)。彼女にはなぜペニスが「ある、または、ない」のか、男を「知らず、または、知っているのか」――それが神秘なのだ。
「自身の行為を言葉で組み立てるには少し早い気がした。言葉は痕跡の上に自然と現れる」(越)と(*8)、「いい表わせぬものが存在するのは確かである。それは自ずと現われ出る。それは神秘である」(6.522)とした「論考」はどう対比さるべきか。ただ一ついえるのは、彼女が「処女∨母」から、限定された「母」への道を着実に歩み始めた、ということだ。それは彼女が近い将来に予期する「自身の行為」を「言葉で組み立てる」ことに他ならない。
「およそ語られうることは明晰に語られうる。そして、論じえないことについては、人は沈黙せねばならない」――「論考」序文の名高く清澄な一節は、私にとっての慰めである。それを今、人をまことに愛することを受け入れた、画家に捧げる。
文中敬称略。なお、本文中『論理哲学論考』の引用は法政大学出版局「叢書・ウニベルシタス」版(藤本隆志、坂井秀寿訳,1968)に拠った。ただし、序文は野矢茂樹訳「岩波文庫」版(2003)に拠る。
(*1)『チャンネル』vol.7,合同会社ch.,2012
(*2)『 ナグ・ハマディ写本 初期キリスト教の正統と異端』Elaine Pagels / 荒井献,湯本和子訳,白水社,1982
ただし、越の引用したものはMalcom Godwin『天使の世界』(大瀧啓裕訳,1993)p.216「死海写本にあるソフィア自身の言葉」とされる一節。
(*3)越ちひろwebサイト『ouroboros』
(*4)「私はこんなふうに描いてきた」(アートブック『Birthday』, 2012)
(*5)『ユング心理学辞典』A.Samuels, Fred Plaut, Bani Shorter / 濱野清志、垂谷茂弘訳,創元社,1993
(*6)『意識の起源史』(上)(下)Erich Neumann / 林道義訳,紀伊国屋書店,1984-85
(*7)実際には排他的論理和(処女∧¬母)∨(¬処女∧母)であり、両立的選言ではない。この場合の「処女」とは限定的に「処女は生物学的母たりえない」ゆえに「母ではない」の置き換えと了解されたい。
(*8)山ノ内町立志賀高原ロマン美術館『ナガノ新コンセプトゥス』パンフレット,2012
なお、同展において「言語=世界」の構造を自覚的に扱っている作家として、松田朕佳(信濃町在住)を挙げておく。
服部洋介 Yousuke Hattori
1976年 愛知県生まれ 長野市在住
文学学士(歴史学)
yhattori@helen.ocn.ne.jp
http://www.facebook.com/yousuke.hattori.14
|