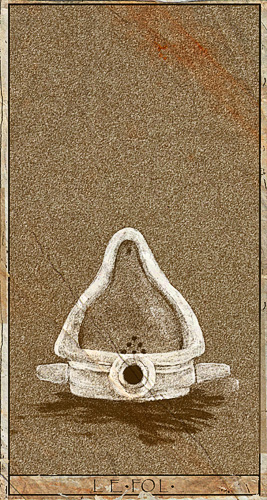|
文 / 服部洋介
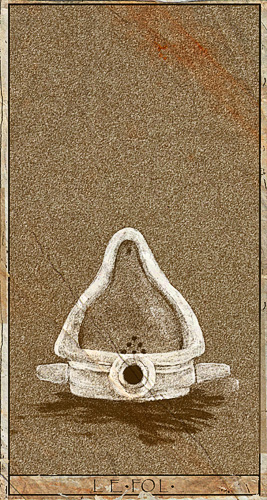 LE FOL
YATSUKA NAKAMURA INSTITUE, 2014
もしこれがトマス・アクィナスであれば、こう問うたであろう。「芸術について、それはいかなるものであり、いかなる範囲に及ぶか」「芸術とは学であるか」と。その『神学大全』第一問第二項の異論①は「学はすべて自明の原理から出発するものである」と主張する。同項の主文は「学には二つの類のものがある」(1)という。ざっくり言うと、理性や知性で確認可能な原理に基づく学と、神からの啓示に基づく学との二つである。後者については、理性の限界を尽くしても理性によっては知りえない原理に基づくものなので、たとえそれが真理を示唆するとしても、バートランド・ラッセルに言わせれば、真理かどうか自体を判別することができない(2)。説明不能なので、とりあえず「信じましょう」ということになる。「信じればいいことあるかもよ?」という〈信仰〉の話になるわけである。
実際、トマスは〈信〉ということを説いている。1273年の四旬節、彼は、ナポリのサン-ドメニコ-マッジョーレの連続説教でこう言った。「自分で認識する以外のことは信じたくないのであれば、たしかにこの世で生活することはできないでしょう。というのも、誰かを信じないでどうして生きていけるでしょう。たとえば、自分の父親はこれこれの人だということをどのようにして信じるというのでしょう。だから人間は自分では完全に知りえないようなことについて、誰かを信じなければならないのである」(3)と。目に見えないものを明らかに知ることはできない。他人が何を認識しているのか、それを私が認識することもない。ヒューム=ドゥルーズの系列では、この「信じる」ということにおいて、〈主体〉は所与を超出したと見なされる。要は、所与の産物である印象や想像を勝手にくっつけたところに〈主体〉が現れるというわけである。トマスは「信じずにどうして生きることができようか」と言った。一方、ヴィトゲンシュタインは、『論考』5.542で「「Aはpということを信じる」「Aはpと考える」「Aはpという」は「‘p’はpという」という形をしていることは明らかである。そしてここで問題となっているのは、ある事実とある対象との対応関係ではなく、対象の対応関係を通じてえられた事実相互の対応関係なのだ」(4)と書いている。彼にとって対象の内心とか思考といったものは「妄想」であって、対象の言葉、著作、対象にまつわる風聞や世評など、対象の実在とは直接関係のない外的な事実のつぎはぎから構成される合成物にすぎない。ひょっとすると、われわれには直接には認識しえないものの、他者による世界の認識とか、意識や思考というものが実在し、かつ、直観なり啓示によって、その真実を知り得るということもあるかも知れない。しかし、その種の真実について、われわれが取り得る態度は、「信じる」か「信じないか」のいずれかであって、これに直接の証明を与えることはできそうにない。デリダもまた〈信〉ということを言っているが、ゆえに彼の〈人文学〉は論証的な〈学〉ではなく、むしろ〈アート〉に近いのである。「本当のところはわからんけど、“この道を信じる”と決めたら、声をあげるべきだ」というわけであって、「1+1=2、それ以外は×」というような唯一の〈正解〉への同一化を拒む、つまりは決定不能性に対する開き直りを決め込んだ哲学なのである。当然、その信じるところの価値とか理念の客観的な証明は不可能。いや、〈事実〉として証明できる方がおかしいぞって話である。
もう一つの問題。トマスによると、「学は自明の原理から出発する」とあるが、自明とはどういうことかというと、これがまったくよくわからない。「確かめるまでもなく当然だ」ってのが自明の語義であるが、ラッセル的には「経験に依存せずに知ることができること」がそれにあたる。たとえば、一般命題「すべての人間は死を免れない」の真偽は、個別の人間の生死からは推論され得ない。この手の全称命題というのは、世界のすべての事例を確認して初めて真偽が判明するものであるから、手持ちの経験的明証のみを根拠としてこれを論ずることはできない。ゆえに、経験によらない一般的真理を表現しようとすれば、ちょっと面倒なことになる。例えば、三段論法であれば「何かがある性質をもち、その性質をもつものが必ず別のある性質をもつならば、その与えられたものはその別の性質をもつ」(5)というややこしい言い回しによって一般化される。ところが、「何か」とか「ある性質」とかに具体的な事物が入ってしまうと、その事物にまつわる原子的事実を確認しなくてはならなくなり、まして複数の個物からなる類だの普遍だのを扱おうものなら、またしても全称命題の堂々巡り。結論から言うと、〈アート〉なる語を一般化することができないのも、一つにはここに原因がある。
トマスのいう〈第二の学〉においては、普遍的真理は、人間理性より上位にある〈神〉からの〈啓示〉によってもたらされる。一方、上に見た通り、一般命題を「何」とか「ある」とか、ナニモノでもない変数で表現することでかろうじて一般的真理に対する知識が担保されているのが理性の限界であるから、現実の命題を構成する各事実については、経験的に確認するか、〈信〉ずるかのいずれかしかない。〈神〉の〈啓示〉が真理であるか否かは理性では確認できない。〈神〉は「汝は面に汗して食物を食ひ終に土に歸らん。其は其中より汝は取れたればなり。汝は塵なれば塵に皈るべきなり」と言っている。人間はすべからく死に、土に帰るというわけだが、この一般的言明については、個別に経験的明証が得られるので、単純枚挙でデータを累積すれば、さしあたって反証も見出されないので、(誤りである可能性はあるけれど)議論の前提として使用して差し支えないと見るわけである。なわけで、人間だとされるイキモノについては、「とりあえず死は免れないんだろうな」ってことでいいんですが、「デュシャンの〈便器〉は〈アート〉ですか?」って話になると、どの時代、どの場所で、誰に聞いても〈アート〉というわけにはいかなくなるので、反証だらけである。結局、〈アート〉、〈ART〉、〈芸術〉などというものが一般に何を指しているのかが問題なのだ。
そこで村上隆は、「〈ART〉とは戦後英米美術である」という公理を打ち立てたわけであるが(なお、国際標準の西欧型〈ART〉は、日本国内で通用している〈芸術〉とは別概念とされる)(6)、もちろん、そこらの人に〈便器〉を見せて「これは〈ART〉としての〈アート〉です」とかって説明は通用しない。そこらの凡人の理解力の問題であることも一因ではあるのですが、じゃあ、何を理解しろってのかというと、「世界のハイブロウである〈ART〉とは戦後英米美術です」という決まりを理解しろって話であって、「じゃあ、なんでそういう決まりになってるのか」って話になると、「戦勝国の文化的価値体系だから」って説明になる。つまり、日本よりも上位の〈神〉であるアングロ・アメリカンの美術観が〈ART〉を規定しているというわけで、その価値を信奉して拝受するならば、〈ART〉もまたトマスのいう〈第二の学〉に該当するというわけである。ラッセルあたりに言わせれば、反理性的なこと甚だしい神秘主義だ。「神秘主義者のいう世界が実在するのかどうかということについては、私は何も知らない。私は、そういう世界を否定したいとは思わないし、いわんや、そういう世界を啓示する洞察などはほんものの洞察ではないというつもりもない。私が主張したいのは(…)、検証もされなければ、具体的な根拠に基づいているわけでもない洞察は、それによってじっさいきわめて重要な真理の多くが初めて示唆されるにしても、真理を保証するものとしては不十分だということである」(7)。よしんば〈ART〉が素晴らしい価値の体現であろうとなかろうと、ンなことは論理的には意味の通らない〈信仰〉だというわけである。もちろん、村上も〈ART〉が唯一絶対の〈アート〉だといっているわけではないし、いわゆる〈アート〉自体の普遍的価値なるものを論理的に解明しようという意図もない。
とはいえ、村上の功績は、実に〈ART〉を〈アート〉や〈芸術〉と明確に区別した点にある。われわれは、これらを混同していたがために、「〈アート〉とは何か」という一般的な問いに答えることができなかったのである。ラッセルは「私の考えでは、新しい論理学は、ガリレオが物理学に導入した進歩と同じような種類の進歩を哲学にもちきたらし、少なくともいかなる種類の問題を人類の知力では及びがたいとして放棄しなければならないのか、わからせてくれたのである。そして、解決が可能であると思われる場合には、新しい論理学は、単に個人的な好みを表わすのではなく、意見を述べる能力のあるあらゆる人が同意しないわけにはいかないような結果を与えてくれる方法を提供することになる」(8)と言っている。〈アート〉の一般化が不可能なのは、〈ART〉、〈芸術〉、〈美術〉等々を含む〈アート〉なる普遍的な類が実在するという自明の信念が、そもそも誤っているからに他ならない。よしや何かしらの類を立てるにせよ、〈ART〉と〈芸術〉は別の類であるというべきであろうし、個人の感じ方、捉え方において〈作品〉の評価が異なるのであれば、〈芸術作品〉なるものは、それぞれに異なった個物として扱わなければならないであろう。ゆえに、個人がある個物を指して「これは〈アート〉だ」と言う時、個人の好みを超えたより上位の価値をあらわす〈アート〉なる共通普遍の概念を価値の根拠として参照することに重大な疑念を生ずるのである。まして、数ある〈アート〉の中で一番偉いのは〈ART〉だという話になると、それはもはや〈神〉からの啓示である。ラッセルは、あっさりとこの種の証明を放棄する。「私たちのより人間的な欲望を満足させようとする希望、つまり、この世界にはあれやこれやの望ましく思われる倫理的な性質が備わっているということを証明したいという希望は、私が理解できるかぎりでは、哲学が、それをかなえるために何かしてあげられるといった希望ではない」(9)と。おっと、〈アート〉どころか、〈神〉のお創りになった〈かくあるべき〉素晴らしい世界の価値もあっさり否定されているではないか。すでにヴィトゲンシュタインで見た通り、〈かくあるべき〉美とか善といった倫理は論証の対象ではないわけである。そういえば、中村教授の口癖も「論理に倫理はない」であった。
〈信〉とは〈かくあるべき〉と念ずることであって、事実確認的な〈知〉とは、真理に対するアプローチが異っている。その成立または不成立が確認可能な〈事実〉と異なり、〈かくあるべき〉は人それぞれであるので、各自の〈かくあるべき〉を唯一絶対の〈かくあるべき〉に同一化させようとする動きがあるとするならば、それはほとんど戦前の大政翼賛会、もしくは昨今のブラック企業である。大人しく権力者の言うこと聞いてりゃいいのに、自由だ権利だとめんどくさい騒ぎを起こすのが、これら〈信〉に基づく〈人文学〉専攻の皆さんなのである。デリダは言った。〈信〉を〈知〉に結び、〈知〉を〈信〉のなかで結び合わせることは、行為遂行的な動きと、事実確認的な動きをたがいに結びつけることであると。「信仰告白、自己拘束、約束、引き受けられた責任、そうしたものは知の言説ではなく、行為遂行的な言説に訴えるのであり、前者が出来事を語るのに対し、後者は出来事を生み出すのです」(10)。原発の立地がどこで、震度いくつの地震がどれくらいの確率で起こって、津波が何メートルなのかというのは、ある程度まで事実確認的と見なされる設問である。そうだとして、じゃあ、原発を作るのか作らないのか、いいのか悪いのかって話になると、各自の〈信〉によるわけであるから、その判断は、人間社会のもろもろを総合した〈人文学〉の領域である。だが、何をどう〈信〉じているのか、言ってることが事実に反してめちゃくちゃなら「データを無視している」と、理系の人に怒られること間違いなしだ。もっとも、事実確認的な〈知〉を尊ぶはずの理系の皆さんも、〈ぐにゃぐにゃの現実〉に巻き込まれたら一巻の終わり、ある意味、趣味的な文系とは違い、カネと成果にシビアな研究環境が仇となり、各国でインチキ論文捏造騒ぎが相次いでいるのは、周知の通りである。ラッセルにしても、第一次大戦には猛反対して投獄されたが、次の大戦では「ヒトラーのほうが戦争の脅威に勝る」として徹底抗戦を叫び、スターリンに対しては西欧の核保有を正当化し、水爆実験に際会するや否や「ラッセル=アインシュタイン宣言」を発して核廃絶を訴えた。人間のすることはぐちゃぐちゃである。
昨今、国立大学法人の人文社会学系の学部が危急の瀬戸際にあるという一件については、すでに述べた。滋賀大学の佐和隆光学長は、その理由を「産業振興に寄与する可能性」が乏しいからと説明する(11)。安倍政権では産業競争力会議が文部科学行政に散々口出しして「役立たず」の人社系諸学部を廃止しようとしているとたいそう憤慨されている。デリダが「〈人文学〉はつねに、学術の世界とは無縁な、収益性が見込まれる資本投資に関係する純粋科学や応用科学の学部のための人質となる」(12)と述べている通りである。ところが、佐和学長は「人文知を役立たずとする発想は、欧州諸国ではありえない」「人文知を修めることが欧州のエリートの必要条件」「人文知を欠く者はリーダーとしての資格を欠く、との「常識」が定着している」と書いていて、ちょっと両者の認識に齟齬がないではないが、それはともかくも、学長曰く、英国では「歴史学専攻の卒業生の多くが、外交官をはじめとする官僚になる」のに対し、法学部出身が主流の日本の高級官僚の多くは、「歴史、哲学、思想などの人文知を欠くため、夜のパーティーでの高尚な会話についていけない」とし、教養的な虚学を重んずる英国に対し、日本の大学の実務系諸学部においては、学生は、歴史、哲学、社会学に無知なまま社会に送り出されてしまうとこれを嘆いている。ちなみに私が学生の頃は、お受験のクソガキどもから、「東大の文学部卒なんて恥ずかしくて履歴書に書けない」と、科類でいえば、文Ⅰに比べて文Ⅲはずいぶんナメられていた。同じ人社系でも、法学、政治学、経済学などは、カネになると値踏みされていたのである。
それはともかくも、〈ART〉と同じで、西欧人の真似をしてパーティーで高尚な(?)会話をすることの何が偉いのかはわからないが、とりあえず、ぐちゃぐちゃな人間社会の現場では、「人文知も少しは役に立つんだよ」っていう傍証として、次のような話もある。先日、仕事の関係である画家と会った際、「欧米では芸術や文化といった人文的な知識がなければ話ができない。その点、日本の理系の方は、もちろん、芸術に理解のある方もいらっしゃるが、概して何も知らない人たちだと思われている」という話を聞いた。この人はフランスを中心に各国で評価を得た画家で、「武蔵野美術大学グローバル人材育成プログラム」の一環として企画された海外の一線で活躍する専門家による集中講義の講師として招聘された人物であるから、それなりのお話である。ちなみにムサビが推進する当該補助事業は、文科省のグローバル人材育成推進事業(Bタイプ)であり、助成額の上限は1億2000万円。いわゆるスーパーグローバル大学である。SGHといい、これ系のネーミングだけは何とかしてほしいものだ。
実は、理系にも人文知が必要だという主張は、今から70年ほど前にもあった。中村博士によると、東工大の学長に就任した和田小六が「これからのエンジニアは社会人文に通じて、世界のこともわかっていなければならない」(13)と言っていたというのだが、博士が入学する前の話のはずである。なわけで、池原止戈夫をはじめ、梅垣寿春、矢野健太郎、永井道雄、宮城音弥、鶴見俊輔、川喜田二郎らがいた頃が、東工大の黄金期だったと博士は振り返る。なお、電気学会会長までつとめながら心霊科学もやっていた後藤以紀も中村博士在学時の教官で、UFOで有名になった大田原治男にいたっては、博士の級友である(笑) 先の佐和学長は、スティーブ・ジョブズ曰くの「人文知と融合された技術」の欠如が、昨今の日本の電子機器メーカーの不振を招いたと主張する。昔の技術者は「ひとかどの人文知の持ち主だった」というわけだ。そういうもんなのかどうなのか、細密な検討はむずかしいが、人文と自然科学、アートの融合が大事だというって話は、なんか楽しいかもね。
「人文知の復権がなされるべき」とは、基本的には〈かくあるべき〉〈信〉の一つである。一方でラッセルは、不断に〈かくあるべき〉限界を突破しようとする。「古い論理学は、いろいろの可能性を締め出して、私たちの想像力をおなじみの世界という壁のなかにおしこめてしまったが、新しい論理学は、起こりうることの方を明らかにして起こらねばならぬことについて断定するのを拒否するのである」(14)。〈古い論理学〉は、その良し悪しはともかく、長らく宗教的な〈信〉を含んでいたため、時には忍従ということが盛んに言われた。「置かれた場所で咲きなさい」などはその最たるものであろう。ラッセルなら、置かれた場所が間違っているなら、場所ごと変えてしまおうと言いだすに違いない。「人間のなしうることにはほとんど限界がないように思われる。死とか、人類が宇宙に存在する力の平衡に依存しているといった人間の力に対する古くからある固定した限界は、忘れられてしまった。そして、いかに無情な事実も、人間の力が万能であるという夢を壊すことは許されない。その願望を満足させる人間の能力に限界を設けようとする哲学は、いかなる哲学でも許されない」(15)。この力強い言明が、彼の論理から自明に引き出される結論かと言われれば違うような気もするが、〈古い論理学〉が偶有的な現実を唯一の真実、必然のものとして受け入れるのに対し、必然といえるのは論理のみであり、一般化された形式のほかに自明のものはないとするラッセルの立場から導かれる一つの〈信〉であることは疑えない。その点、可能世界の中から〈神〉が最善を期してこの世を創ったとするライプニッツとは対照的である。〈神〉においては、ユダの存在さえ、より大きな善を実現するための布石なのだ。とりうる手段を考えれば、ラッセルなら「いや、ユダとかいなくてもなんとかできるでしょ」と言うところだが、そこは〈神〉しか知りえない複雑な流れというのがあって、「あんたも置かれたところで咲いてなさい」というか、それ以外にどこへも行き場がないというのが、〈かくあるべき〉世界の極点なのだ。それはそれでそんなような気もしないではない。なぜなら、〈かくあるべき〉現実の世界のほかに、過去に別の可能世界が実現しえた目に見える証拠というものも確認できそうにないからだ。
一般化することのできない〈アート〉の価値や性質を、あたかも一般命題のように語ることによって、〈アート〉はほとんど〈神〉の座を占めてきたように見える。それはまた、ひとり〈アート〉の問題ではなく、あらゆる〈価値〉は〈信仰〉によって支えられており、トマスのいう〈第二の学〉としての性質を備えていることについて見てきた。それは基本的にはぐちゃぐちゃの〈人文学〉であり、その対象となるのは何らかの外的な〈事実〉ではない。それが生み出すのは、〈神〉的な価値を表現した〈作品〉なのである。デリダは〈来たるべき人文学〉において言う。それは「肯定的かつ行為遂行的な仕方で批判的な問いを立てる権利、すなわち、数々の出来事を生み出すことで――例えば、何かを書くことで――、特異な作品をもたらすこと(これは今まで、古典的ないし近代の〈人文学〉の範疇には入りませんでした)で批判的な問いを立てる権利なのです」(16)と。〈神〉は一人ではない。先人の説、すなわち〈事実〉を一字一句踏襲して、その言い草を信奉するのが〈来たるべき人文学〉の使命ではない。〈作品〉によって〈事実〉を生み出すという、およそ〈神〉的な創作、〈アート〉こそが〈人文学〉の特権なのだ。自然科学でそれをやったら捏造だが、〈信〉にもとづく〈人文学〉においては、人間の数だけ信仰があり、価値や解釈が異なるのは当然のことである。従って、物言わぬ自然に対してこちらの認識を押しつけても文句は言われないが、人文において他者を我有化するということは、ヴィトゲンシュタインが言うように初めから妄想であり、にもかかわらず認識の主体と対象において真の一致が成り立つというのなら、その理性的な確認手段を教えてほしいものである。こういうことは〈信〉ずるほかないのであり、〈信〉じたことを〈無条件に〉公言することのできる〈歓待性〉というものが〈人文学〉の場にはぜひとも必要だというのである。したがって〈信〉が唯一とされるなら、すべては単一の信仰に同一化され、〈歓待〉は実現されえない。「これがアートだ」「あれはアートじゃない」というのは、どれだけ上位の権威に発する決めつけか知らないが、早い話が、やな上司の、けれども逆らっちゃいけない建前のよくわからない命令のようなものだといえば、おわかりいただけるかと思う。従って、〈信〉はその根底にある我有化の欲望から分離されなくてはならないのであるが、それは定義的に不可能である。その不可能性に根差したおかしな総体を〈脱構築〉と呼ぶわけである。
〈アート〉の〈価値〉や意味内容が普遍的なものとされるならば、それは我有化に基づく〈信仰〉である。トマスは言う。「人間理性による論証は、信仰に関することがらを証明するには無力である。(…)理性によって信仰を証明(…)すれば信仰の価値は失われるであろう」(17)。一般化できないものを一般化する、つまり我有化による〈事実〉の記述は、〈信仰〉としては差し支えないが、論証はされえない。その意味で、トマスは明確に理性の限界を知っていた。面白くも何ともない話だが、これがトマスの示した重要な結論である。答えていわなければならない。〈アート〉は〈第二の学〉であり、その〈公理〉は常に〈啓示〉によってもたらされるのである。
(*1) (*17)世界の名著 続5『トマス・アクィナス』Thomas Aquinas〔著〕,山田晶〔編〕,中央公論社,1975,p.85,104
(*2) (*5) (*7) (*8) (*9) (*14) (*15)世界の名著58『ラッセル・ヴィトゲンシュタイン・ホワイトヘッド』Bertrand Russell,Ludwig Wittgenstein,Alfred Whitehead〔著〕,山元一郎〔編〕,中央公論社,1971,p.104,142,104,145,109,93-94,112
(*3)『人と思想114 トマス=アクィナス』稲垣良典〔著〕,清水書院,1972,p.79-80
(*4)叢書・ウニベルシタス6『論理哲学論考』L. J. J. Wittgenstein〔著〕,藤本隆志,坂井秀寿〔訳〕,法政大学出版会,1968,p.163
(*6) 『芸術闘争論』村上隆〔著〕,株式会社幻冬舎,2010,p.123
(*10) (*12) (*16)『条件なき大学』Jacques Derrida〔著〕,西山雄二〔訳〕,有限会社月曜社,2008,p.20,16,12
(*11)信濃毎日新聞,2015年6月22日付朝刊
(*13)筆者との対話,2011年11月8日,2014年3月28日
服部 洋介 Yosuke Hattori
1976年、愛知県生まれ。
長野市民。
yhattori@helen.ocn.ne.jp
http://www.facebook.com/yousuke.hattori.14
|